サブタイトルはローランド・マーチン氏の著書『Roland Martin’s 101 Bass-Catching Secrets』より引用しております。
同著書は電子書籍としても発行されておりますので、御一読いただくことをおすすめします。
私もこの著書を読むまでは、その理由を深く考えたことはありませんでした。
せいぜい捕食、威嚇、好奇心程度の認識でしたが、他の要素と、さらにそこを細分化して考えることにより狙うべきサカナに対するアプローチも変わってきます。
Nine Behavioral Reasons Why Bass Strike
ここに、氏が挙げた9つの理由を記しておきましょう。
- Feeding(捕食)
- Reflex Action(反射行動)
- Anger(怒り)
- Protective Instinct(保護本能)
- Curiosity(好奇心)
- Competition(競争心)
- Territorial Instinct(縄張本能)
- Killer Instinct(殺害本能)
- Ignorance(無知)
威嚇行動
この中で私が特に混同していたのはAnger(怒り)とProtective Instinct(保護本能)、Territorial Instinct(縄張り本能)です。
Protective Instinct(保護本能)は、いわゆるベッドフィッシングやフライガードのオスに対するアプローチなどが挙げられます。『種の保存』に対する本能とお考えください。
Territorial Instinct(縄張り本能)は、スポーニング期とは関係なく、捕食や生存競争に勝つための縄張を持った、あまり動かないサカナの『個としての生存』を主とした本能です。
わかりやすく言い換えると『稚魚を守るための行動』と『自分の生存のための行動』の違いであり、最終的にこれがAnger(怒り)となってルアーやサカナなどに対してのアタックに繋がるというのが私の解釈です。
具体例については別途記事にしていく予定ですので、今回はその他のケースについて先にまとめていきます。
好奇心と無知
次に混同されやすいのがCuriosity(好奇心)とIgnorance(無知)ですが、Ignoranceに関しては、現状のフィールドにおいて、ほぼ残っていない状態と言えますので、自分のアプローチに組みこむことは無いでしょう。
もし今後、プライベートポンドなどで釣りができる機会があれば、この2つの差異を学べるかもしれません。
Curiosity(好奇心)に関しては、Anger(怒り)による威嚇アタックとも混同しがちなのて、この具体例も後日執筆する予定です。
殺害本能
そして、いまだに理解できない行動――それがKiller Instinct(殺害本能)です。氏曰く「マスキージッターバグなどの、とても口に入りそうもない巨大なベイトに対し、小さなバスさえもアタックしてくるのは殺害本能によるもの(意訳による要約)」と記されています。
ビッグベイトやマグナムベイトなどに対するサカナの行動を見ていると、Curiosity(好奇心)ともAnger(怒り)ともReflex Action(反射行動)とも取れる反応を見せますが、「これこそがKiller Instinctだ」と確信できる状況に巡り会ったことはありません。
事実を知り、向き合うこと
バスを擬人化することを好む人たちにとって、このKiller Instinct(殺害本能)という性質は耳障りのよくない言葉かもしれません。
しかし、自然界の生存競争においてバスに限らず同種殺しや共喰いは日常的に起こりうることであり、そこに人間の倫理観を持ち込むこと自体がナンセンスであると私は考えています。
卵や稚魚の状態ではエビやゴリ、他魚種の捕食対象となるバスも、成長するにつれてそれらの非捕食者を喰うようになるのが自然界の摂理であり事実。
孵化直後のフライをオスが守っている状態で、そのフライを喰う天敵の1つが同種のバスであるというのも事実なのです。
それを知らずして、そこから目を背けて学ぼうとしても結論にたどり着くことはできません。
「スレきったバス」を「天才バス」と表現していては、そこから先に進むことはできないでしょう。なぜなら「頭がいい」のと「極度の緊張状態による怯え」はまったく異なる状態にあるからです。
氏が最後にIgnoranceを記した理由、それは釣り人に対して「無知であり続けてはならない」という著者の深意があったのでは?と私は推察しております。
自然の摂理――本能を刺激するためのヒントを学ぶことができたローランド・マーチン氏とその著書に敬意を表すと共に、これからの課題として釣りを楽しんでいきたいと思います。
Roland Martin氏のウェブサイト

コメントについて
このブログでは承認制でコメント欄を解放しておりますが、以下のような書き込みについては非掲載、もしくは予告なく削除し、場合によってはIPアドレス等によるアクセス制限を掛けますのでご了承ください。
誹謗中傷
批判や批評と誹謗中傷は異なります。
品位に欠けるコメント
いわゆるタメ口も含みます。たとえ賛同意見であっても「ですます調」を使えない方の書き込みは削除します。
環境問題および外来魚・移植魚問題などに関して
カテゴリー『環境問題』に分類された記事にのみ書き込みを許可します。その他記事への該当コメントはすべて削除します。
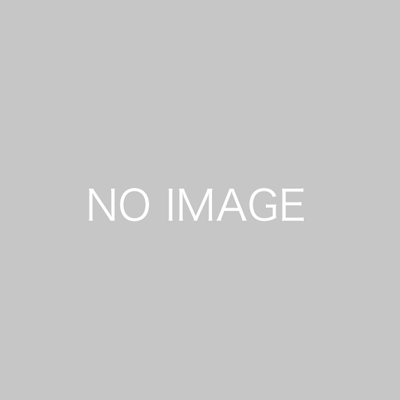

コメント